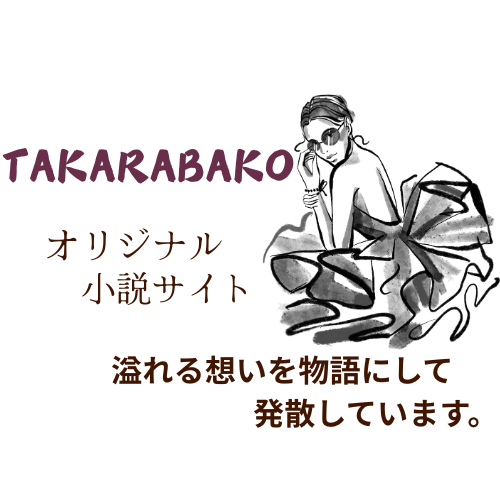「あの時の、弟さんの絵を見ていた恭ちゃんの横顔、
カッコ良かったなぁ~ こんな風に顎に手を当てちゃって…、ふふっ。」
リナが、腰に手を当て、もう片方の手を顎につけて気取った顔を見せた。
「なんだよリナ、まだ俺をからかうつもりか…?」
「からかってなんかないわ、ただ、ホントにカッコ良かったって話よ。」
「それはそれは、光栄です。」
俺は、次にリナが何を言ってくるか、何となく分かっていた。
リナは、テーブルに両肘を付き、そして両手に頬をのせた。
そして、小悪魔の様な可愛い顔で小首を傾げ、俺を見つめた。
「恭ちゃんは?」
「何が…?」
わざと俺は、とぼけた様に聞き返した。
「もぉ、何って…、初めて私を見た時の感想よ。どう思った…?」
やっぱり俺の予想は当たった。
すぐ両隣に人がいるカフェで、イチャイチャ話しをするのが苦手な俺は、
リナの思惑を敏感に察知し、回避する術を学んだ。
「う~ん、あの時は急に話しかけられたから…、びっくりしたって事は
覚えてるよ。」
リナは、俺の言葉をガン無視して即座に攻撃を仕掛ける。
「可愛いと思ったか、可愛くないと思ったか…ハイッ、どっち?」
少し苛立ち始めたリナの表情が可愛くて、俺は再びとぼけた回答でじらす。
「そうだな~、特に可愛いかと聞かれたら可愛いかったと言えるような
言えないような、逆にか、、、」
「もぉいい、恭ちゃんなんか嫌いっ。」
痺れを切らしたリナが片方の頬を膨らませ、プンプンしながら
タブレットを開いた。
「デザート頼んじゃおっと、これで太ったら恭ちゃんのせいだからね。」
リナはブツブツ言いながらも、やがて大好きなスイーツを嬉しそうに
選び始めた。
俺はそんな彼女が愛おしくて、暫く見つめていた。
そして、初めて会ったあの日の事を思い返した。
*************************************
弟の絵を見ていたリナは、帰ろうとする俺に、『友達が来るまでの間、時間を
潰したいので、どこか喫茶店でもあったら教えてほしい』と言ってきた。
展示場からそう遠くない場所に、レトロな雰囲気の喫茶店があり、そこまで
彼女を案内した。
「よかったら、一緒に温かい物でも飲んでいきませんか?」
そう誘ったのはリナだった。
俺はその頃、保険会社に入社して1年位たったが、成績はさっぱりだった。
当たり前だが、ホストの営業と保険の営業は全く違うものだった。
俺はどこに行っても使い物にならないクズなのかと不貞腐れていた。
しかし、この日ばかりはアポイントが1件も入っていなくて、逆にラッキーだった。
喫茶店で向かい合って座ったリナは、弟の絵について目を輝かせながら
絶賛した。
「サッカーは今もやっているんですか?」
リナは、弟の絵の話が一旦落ち着くと、俺の方に真っすぐ視線を向けて聞いた。
「いえ、中学生まではやってたんですけど、高校入ってすぐ足を怪我しちゃって、
続ける事が難しくなって辞めたんです。」
リナは「嫌なことを思い出しちゃったらごめんなさい」と
申し訳なさそうな顔で言った。
「いいえ、昔の事ですから、気にしないでください。」
そんな風にカッコつけて言ったが、実は嘘だった。
俺はサッカーの強いことで有名な高校に入り、早速サッカー部に入った。
まさに期待に胸を膨らませていたが、練習が始まって暫くすると、
自分は思ってた程、上手くないんだという事に気付かされた。
つまり、俺よりも凄い奴が大勢いたって訳だ。
人生で初めて味わった挫折だった。
1学期が終わると俺はサッカー部を辞めた。
サッカーをやめ、高校生活は問題ばかり起こすようになり、母親が学校に
呼び出されることも少なくなかった。
俺の転落人生はそこから始まった。
何とか大学だけは行って頂戴と母に言われ、名も知らない地元の私立大学に入った。
そして、ろくでもない大学生活を終え、冴えない人生はずっと継続していた。
リナは、そんな俺の前に不意に現れたまさに女神だった。
体内にこびりつき、ドロドロと細胞に浸潤するヘドロを、一瞬で聖水の如く、
浄化してしまう程の威力を秘めたリナの笑顔に、俺は心を鷲掴みにされたのだ。
「あ、友達が着いたみたい、私戻らなきゃ…、」
スマホをしまってリナが立ち上がった。
(待て…、これでサヨナラなんて、嘘だろう? 引き止めろ。)
俺は焦った。
(女を口説くなんて朝飯前だろ。)
頭が真っ白になって、言葉が出てこない…。
リナが会計を済ませ、出口に向かう途中で、俺はやっと声が出た。
「あの…、また、僕と逢ってもらえませんか…?」
それまで、多くの女を口説き落としてきた俺が、初めて使った言葉だった。
リナは一瞬驚いた顔で俺を見つめ、ニコッと微笑んだ。
その笑顔のせいで、俺の心臓が2倍の速さで動き出した。
「連絡下さい、、、待ってます、、、。」
俺は震える手で名刺を渡した。