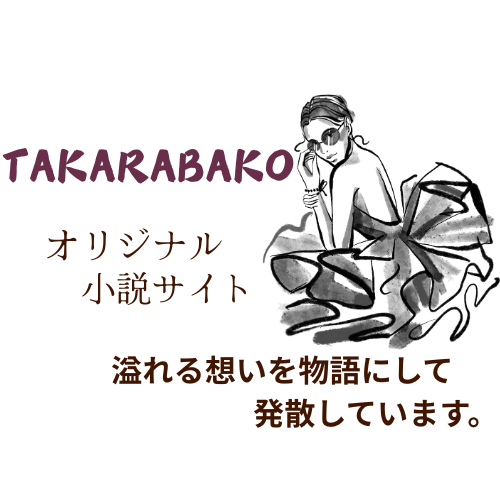************************
翌日の日曜日、俺はリナと、行きつけのカフェでランチをしていた。
「私、恭ちゃんが自分のこと『俺』って言ってる事なんて、
とっくに気付いてたわよ。時々言い間違えてたもの。」
リナは、メロンソーダに浮かんだアイスクリームを、ストローで
突きながら平然として言った。
「へ? あ…、うん。昔は『俺』って言ってたんだけど、最近はほら、
仕事で『わたし』とか、『ぼく』って言うだろ? だからさ…。
別に、隠してたわけじゃないんだけどね。」
俺は少し気まずかったが、平然を装って言った。
普通なら『俺』とか『僕』なんてどうでもいい話だが、俺は
そんな些細な事ですら、リナの前では気を使ってしまうのだ。
「じゃあ、これから私の前では俺って言ってね。」
「別にいいけど…どうして?」
「う~ん、なんとなくそっちの方がしっくりくるから。」
「分かった。じゃあ、俺…でいくわ。」
「うん。」
リナがニコッと笑って「もう一回、言ってみて。」と言った。
「え、嫌だよ…、後で言うよ。」
「お願い、いいでしょ…? 今聞きたいんだもん。」
リナの妙なお願いが始まった。
時々リナは、こうやって俺をからかって遊ぶのだ。
「俺…。」
仕方なくリナの要望に応えた。
「ふふ、ありがと…、恭ちゃん大好きッ。」
リナが屈託のない笑顔でさらりと言う。
自分の顔が一瞬で赤くなったのが分かった。
俺は咄嗟に「トイレ行ってくる」と席を立った。
トイレの洗面所でジャブジャブ顔を洗った。
まったくどうしようもないほど、俺はリナに夢中だった。
「俺、ダッセェ…。」
こんなところを昨日の奴らに見られたら、一生馬鹿にされるだろうな…。
席に戻ると、何やらリナが1枚の名刺を見つめていた。
見ると雅也の名刺だった。
俺への当てつけのつもりだろう…いかにも奴のやりそうな事だ。
「恭ちゃんもホストやってたなんて、ちょっと驚いちゃった。」
俺がホストをしていた事を、リナに内緒にしていると見越して、
わざと雅也は話したのだ。
まぁ、最初から覚悟はしていたけど。
「でも、1年も続かなかったよ。」
「ふ~ん、恭ちゃん売れっ子だったの?」
「売れっ子? ハハ、全然ダメだったよ、
雅也にしつこく誘われて仕方なかったんだ。」
「全然売れなかったんだ…。残念でした~。」
リナは嬉しそうに笑って言った。
「でも、恭ちゃんイケメンだから学生時代はモテたでしょ?」
「モテないよ。」
「嘘ばっかり。」
「リナ、今日はどうしたんだ?やけに攻めてくるな…。」
「え、だって…、だって、昨日、恭ちゃんの意外な過去を聞いたら、
なんだか、もっと知りたくなっちゃったんだもん…。」
リナは少し拗ねた様な表情で俺を見つめた。
そして、暫くすると思い出したようにニヤッと笑って言った。
「ねえ、恭ちゃん、私と初めて会った日のこと覚えてる?」
「えっと、確か、どっかの展示会場だったよな…。」
忘れるわけがない…。
あの日は美大に通っていた弟から、卒業制作の展示会があるから
絶対に見に来てと頼まれ、俺は仕事の合間に行くことにした。
弟の絵は、少年達がサッカーをしている様子を描いたもので、
まるで写真の様な描写で描いてあった。
生まれつき体が弱い弟は、俺が友達とサッカーをしている時も必ずついてきて、
公園の隅で絵を描いていた。
俺は弟が可愛くて、よく遊びに連れまわして母親に叱られた事もあった。
俺は絵心が全くないが、弟の描く絵だけは好きだった。
ふと下を見ると、そこには『兄』と題名がつけられていた。
一瞬熱いものが込み上げたが、グッとこらえて立ち去ろうとしたその時、
すぐ隣で、弟の絵を見つめていた女性に気が付いた。
俺は驚いて、思わず声を上げそうになった。
その女性がリナだった。
「この方、きっとお兄さんが大好きなんでしょうね。」
「え…?さ、さぁ、どうでしょう…。」
気付いたら俺は、言葉を交わしていた。
「私はそう思いますよ。」
リナは澄んだ瞳で答えた。
「だと嬉しいですが…、弟なんです。」
「え?お兄さんだったなんて、失礼しました。でも凄い偶然ですね。」
リナは瞳をきらきらさせて感激していた。
俺は、彼女のあどけない笑顔に釘付けになって、ただ呆然と立ち尽くしていた。