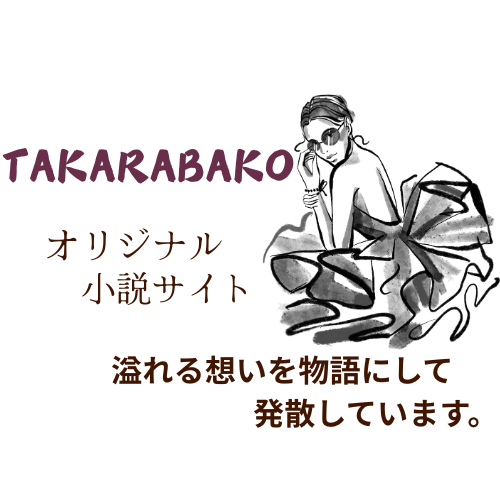「恭ちゃん…起きて。」
リナの可愛い声を、平日の朝から聞けるこの幸せを、俺はベッドの中で
ゆっくりと味わっていた。
新婚旅行から戻り、親戚への挨拶も済ませ、今日から日常の生活に戻る。
新婚生活の始まりだ…。
食卓に着くと、美味しそうに焼けたクロワッサンと卵焼きが
用意されていた。
「卵が上手く焼けなくて、つぶれちゃった. 形が悪くてごめんね。」
リナがコーヒーカップをふたつ持って、キッチンから出てきた。
「わ、うまそう!形なんか関係ないよ。」
「そぉ…?有難う。じゃあ恭ちゃん、早く食べて食べて!」
俺は、少し潰れて卵の黄身が飛び出してるそれをフォークで刺し、
口の中に放り込んだ。
「お、結構スパイスが効いてて、旨いよ!」
「う、うん、ちょっとお塩掛け過ぎちゃった…」
「いいよいいよ、俺は濃い味が好きだし。」
「ごめんね、でも、そう言ってくれて嬉しい!ありがと。」
リナと一緒に朝を迎え、リナの作った朝食を一緒に食べる。
そしてこの可愛い笑顔が見られれば、それでもう十分なんだよ…。
俺は口の中にジャリジャリと残った卵の殻を、コーヒーと一緒に
ゴクリと飲み込んだ。
「あ、恭ちゃん時間大丈夫?」
時計を見るとまだ少し余裕があったが、新婚でのぼせ上がってると
思われるのも嫌なので、今朝は余裕をもって早く出ることにしよう。
リナのインテリアセンスが最大限に活かされた二人の新居は、
とても快適なうえに、生活用品の全てがあるべき場所に収まっている。
毎朝バタバタと探し物をしていた独身の頃とは大違いだ。
俺は何のストレスもなく、すんなりと支度が済んで、
鏡の前で化粧をしているリナを見た。
言うまでもないが、リナはすっぴんでも十分可愛い。
彼女のほんのり赤みを帯びた唇が、口紅をひくと、
さらに潤いが増して、ぷっくりとしたピンク色になった。
今まで俺に会う為に、彼女がこんな風に鏡の前で化粧を
していたのかと思うと、なんとも嬉しい気持ちになった。
いや、待てよ…、でも、これからは…。
俺は一瞬モヤモヤしたものが胸のあたりでうごめいた。
彼女は誰の為に、あんなに可愛く化粧をしていく必要があるのだ?
今日、彼女は俺のもとに帰って来て、この化粧は落としてしまうのに。
「リナ、化粧しなくても可愛いよ。別にしなくてもよくない?」
「うふ、ありがとう、恭ちゃん大好き。」
リナは俺に抱きつき甘えた声で言ったかと思うと、いそいそと
クローゼットの方に行ってしまった。
「あ、リナ、今日は生ごみの日だって言ってなかった?
俺持っていくよ。」
そう言ってキッチンに向かった。
シンクの三角コーナーには、まだ生ゴミがたまっていた。
たぶん朝食で作ったサラダと卵焼きのゴミだろう。
トマトやパプリカの切れ端がシンク内に散らばっていた。
フライパンやフライ返しなどのキッチン用具も洗い桶の中に
入っており、油の浮いた水に浸かったままだった。
三角コーナーから、卵の殻が溢れ出ていた。
あれ、こんなに卵、使ったのか?
そんな事を考えて立っていると、リナが慌てて走って来た。
「やだ、恥ずかしいから見ないで! 今朝、なかなかうまく卵が割れなくて、
何度か失敗しちゃったのよ…、あ、あと、洗い物は帰ってからやるわね。」
リナは素早くポリバケツから生ごみの入った袋を取り出し、
家じゅうのゴミを集め始めた。
「じゃあ、今日はゴミ、恭ちゃんお願いね。私はカギを閉めて
出ていくから先に出て。」
「あ、うん、オッケー。じゃあ、行ってくるね。」
「行ってらっしゃい。」
リナは大慌てで支度をした割には、完璧にコーディネートされた
衣服を身にまとい、いつもと変わらぬ笑顔で送り出してくれた。
久しぶりに出勤すると、案の定結子さんがすっ飛んできて、
「あとでランチしようね!」
とニコニコ顔で耳打ちした。
「よう、若旦那、幸せに浸るのも結構だが、今月はあと半月しかないからな。」
パソコンに視線を落としたまま、柏木リーダーは厳しい言葉を投げかけた。
「はい、もちろん分かっています。進捗状況をすぐに提出します。」
俺は喫煙室に入ると、安堵のため息と共に、煙をゆっくり吐いた。
まずは、家庭という土台が出来た。
この先の我が家の生涯設計プランを考えるとワクワクが止まらない。
俺は、リナの旦那として、自慢できる男になりたかった。
とにかく、俺に出来る事は、仕事だ。
営業マンとして、今よりも結果を残せる男になりたいし、
もっと稼いで、リナに贅沢をさせてあげたい…。
俺はタバコを灰皿に押し付け、喫煙室を出ると、急いでリーダーの元へ
向かった。
「え、K社…?」
「はい、なかなか、会ってもらえなくて…。」
「あそこは先代の頃から、地元との交流を大切にしている会社だから、
商店街の会合や行事にも頻繁に出席する必要があるけど、大丈夫か?」
「特に問題ありません。」
「息子が事業承継したばかりだから他社も狙ってるぞ…。
まぁ、そこで上手くいけば報酬もがっぽり…だけどな。」
「リーダー、俺、やります!」
「流石、ベタ惚れした女を妻にした男は違うな~。」
「そうですよ、そのうちリーダーの席も、俺が頂くつもりなんで、
その時はよろしくお願いします。」
リーダーにからかわれた俺は、ムカついた勢いでそう豪語した。
「ハハハ、望むところです。」
愉快そうに笑顔を見せるリーダーに背を向け、俺は会社を後にした。
商談が長引いてしまい、もう外は暗くなってしまった。
それでも、家に帰れば愛する妻が待っている。
俺はリナに会いたい一心で、気付いたら駅から
猛ダッシュで家に向かっていた。
「リナ、ただいま~。」
俺は元気に声を張り上げた。
「お帰り、あー、もぉ!」
しかし、リナの声はどこかぶっきらぼうで酷く苛立っていた。
さらに家の中は、何かが焦げた匂いと煙で充満していた。
恐る恐るキッチンを覗くと、食材と調理器具が散乱した中で、
リナが包丁を片手に、キャベツを飛び散らせながら切り刻んでいた…。