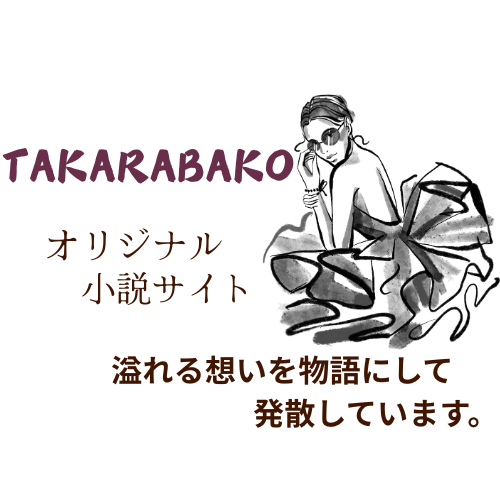父は、毎日母が何処かに出かけていると思っている。
「お母さんは?」と聞かれるたびに、私が「出かけてる…。」と
答えているからだ。
本当に母はどこかへ出かけているのだ、と思いたい…。
あの日、母から電話で癌になったことを告げられた。
******************************************
「わたし、癌になっちゃった。」
すぐに返事が出来なかった。
頭の中が真っ白になった。
そんな私の返事を待たずに、スマホの向こうで母は喋り続ける。
「それでね、結局手術が出来ないから抗がん剤治療をしましょうだって。
髪の毛も抜けちゃうでしょう?本当に嫌になっちゃう。」
「それで…、大丈夫なの…?」
そんな言葉しか出なかった。
「心配いらないのよ。ただ、入院が必要だっていうから、
お父さんのこともあるし…。」
そうか、母は自分が留守の間、父が一人になってしまうことが心配なのだ。
「美香、悪いけど1ヶ月位こっちに来てもらえる?」
急に母の口調が申し訳なさそうに重くなった。
さっきまで普通に癌治療の話しをしてたというのに。
「大丈夫よ、お父さんでしょ?任せてよ。」
「でも、武史さんは大丈夫?」
「武史なら全然平気、かえって一人の方が気楽だって言うかも。」
自分でもびっくりするほど陽気な声がでた。
「悪いけどお願いね。武史さんにもよろしく伝えてね。」
そう言って母は電話を切った。
母との電話を終えた私は、しばらくその場に立ち尽くしたままだった。
急に不安と恐怖の感情がこみあげてきて、吐きそうになった。
ずっと恐れていたことがこれからおきる気がしたのだ。
この時、母の癌はかなり進行していた。
癌は母の細胞を容赦なく蝕んでいき、抗がん剤治療と闘う力さえも
奪っていった。
母は、持ち前の華やかさの他に落ち着いた雰囲気もあり、
周りから一目置かれる存在だった。
父との結婚を機に手に職をつけたいと、子育てをしながら洋裁教室に通った。
家族や自分の服を作っては「素敵でしょう」と、得意げに笑ってみせた。
自宅の一部屋を利用して、洋裁教室を開き、やがて教室を閉めた後は、
父や友達と旅行に行くなど、第二の人生を謳歌していた。
私はずっと、そんな母が大好きだった。
子供達に面倒をかけることが嫌いな母は、自分の体調不良についていつも話さない。
以前もポリープで入院したが、知らされた時は退院後だった。
もし、父のことがなかったら、母は癌の事を私に話しただろうか…。
******************************************
「美香は、武史君とどうするつもりなんだ?」
不意に縁側の父が私に声をかけた。
「え、どうするって、もう…。」
武史とはもう離婚したのだ。
母の葬儀が終わって暫くして、正式に離婚をしてこの実家に引っ越してきた。
いわゆる出戻りだ。
「結婚するんだろ? 彼の事はお父さん達も大賛成だよ。」
「え…? あ、うん、そうね、ありがとう。」
父は楽しそうに笑みを浮かべながら庭に視線を戻した。
私はそれ以上何も言わなかった。
この家に戻ってきて、父に離婚した事を告げた時、
「そうか、美香が決めた事ならお父さんは何も言わないよ。」
そう言って、私の頭をそっと撫でた。
その時の父の寂しそうな顔を、私はもう二度と見たくない。
ここで本当の事を言ったとしても、また数分後には忘れてしまうのだ。
認知症とは残酷なもので、最愛の妻の死も、娘の離婚も、
知らされる度に、悲しみと対峙しなければならない。
それなら、わざわざ本当の事など言わなくていいのだ。
私にとってもその方が都合がいい…。
本来であれば、どの面下げてと言う所、父が認知症だからこそ、
私はこの家に戻ってこれた。
今はこのまま父の記憶に甘えてしまえばいい…。
気が付くと私は、縁側で寛ぐ父の傍に座り込み、
自分の過去の記憶を振り返っていた。