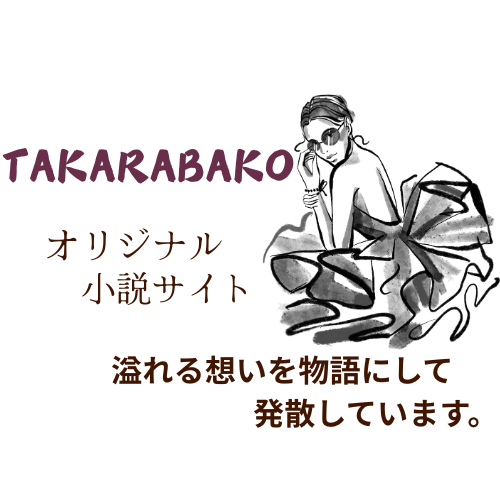「お疲れ様、美香。」
武史が、こっちにおいで、とソファーをポンポン叩いた。
「それじゃあ、ハーブティーでも淹れようかしら。」
私は自分でも驚くほど、弾んだ声で返した。
義父母を招いた一大イベントをやり遂げ、安堵の気持ちで
心が満たされていたせいかもしれない…。
ハーブティーを淹れたマグカップを持って、武史の隣に腰を下ろした。
「あぁ、やっと美香とゆっくり話せるよ。」
「そういえば、帰国してから年末の買い物やお正月の準備で、
ゆっくり話も出来なかったものね。」
「俺、クリスマス寂しかったな〜。美香と一緒にいたかった…。」
「でも、クリスマスをニューヨークで過ごすなんて素敵じゃない?
よかったら、どんな感じだったか教えて頂戴。」
武史は私の問いに答えようともせず、つまらなそうに呟いた。
「美香はどうせ実家が楽しくて、俺の事なんかこれっぽっちも
思い出さなかったんだろうな…。」
武史が拗ねた顔で私に寄り掛かる。
「そんな事ないわよ、LINEだって何度もしたでしょ?」
「美香からはたったの2回ね、俺は何度もしてるのに…。」
武史の恨み言が続く…。
「ごめんなさい…。お仕事の邪魔になると思って控えたのよ。」
すると武史はクスッと笑い、「わかってる、ほんの冗談だよ。」
と言って、テーブルのマグカップに手を伸ばした。
「来年のクリスマスは一緒に過ごせるといいわね。」
武史の機嫌が治って、少しホッとしながら何気なく言った。
「来年は絶対一緒にいられるよ。」
すると彼は得意げな顔で言い放った。
「分からないわよ、実際今までクリスマスは海外だったもの。」
「美香…、実は俺、転職することにしたんだ…。」
「あら、そうなの? でも、ずいぶん唐突ね。」
「ごめん、なかなか話すタイミングがなくて…。」
「いいのよ、お互いに忙しかったし。」
「ベンチャー企業の社長から、うちに来ないかって言われてたんだ。
前から挑戦したかった分野だったんだけど、今のキャリアも十分
活かせると思って、今回正式にオファーを受けることにしたんだ。」
「そうなの、武史が決めた事なら私は賛成よ。」
「ありがとう、美香はそう言ってくれると思ったよ。」
武史は安心した様子でソファーに横になり、私の膝の上に頭をのせた。
「これで子育ても一緒に出来るな。」
「武史ったら、気が早いわよ、転職して落ち着いてからでも…。」
「そうだけど…なんてゆうか、美香と早く落ち着いた家庭が
作りたいんだよね、俺は…。」
「今だって、私は十分落ち着いてると思うけど…。」
「でも、俺は満足してないし、もっと美香に必要とされたい。」
武史はソファーから身体を起こし、怪訝そうに私を見ながらぽつりと言った。
「美香はいつも冷静だね。」
「えっ…、冷静ってどう意味…?」
その時、私の中で嫌な記憶がよみがえった。
クリスマス・イヴの夜に母から言われた言葉だ。
ーーーー 美香は意外にクールだから…。
あの夜、その言葉がまるで矢の如く私の自尊心を貫いた。
私はいつだって母の望むように努力してきたつもりだった。
そんな私に対して、あの言葉はどんな意味が込められていたのか、
未だにどうしても納得がいかないのだ。
そしてまた、あの時と同じ苦々しい思いで武史と向き合っている。
「そんな怖い顔しないでくれよ、美香。」
武史は慌てて私の頬をぷにっとつまむと、クスッと笑った。
「ごめんごめん、冗談だよ。」
私は思わず涙が出そうになるのを必死でこらえた。
私はただ、悔しかった。
こんなに頑張っているのに、なぜこんなに悔しい思いをしなければ
ならないのか分からない…。
私は武史の良い妻にはなれないのか。
もう、二度と失敗は出来ないのに…。
まったく、どうしたら良いのか分からなくなってしまった。