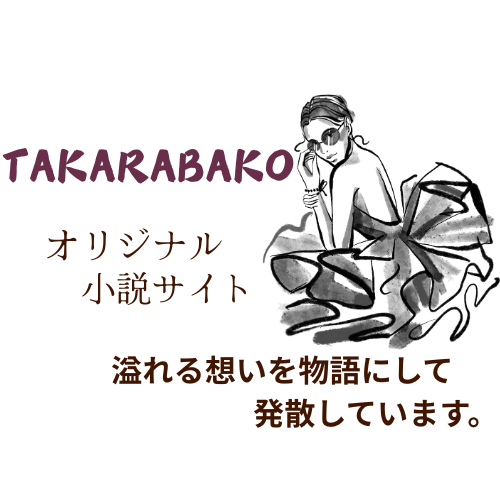砂場から離れ、公園の中央付近まで来てふと思った。
まだ公園に来てから30分も経っていない。
このまま戻ったら、由美子が変に思うかもしれない。
それに、尚人も俯いたままじっと私の手を握っている。
こんな状態で家に帰るわけにはいかない…。
私が立ち止まって、どうしたものかと考えあぐねていると、
「ミカ、鉄棒!」
そう言って尚人が走り出した。
行ってみると、鉄棒がズラリと横に広がっており、端から段々と高くなっている。
尚人は一番端の鉄棒に、腕を掛けたり片足を上げたりして遊んでいる。
そのうち、動物の形をしたシーソーに、「ミカも乗れ。」と言われ、
二人で暫く遊んだ。
そうこうしている間に、公園内にいる人の数も少なくなってきた。
尚人は、誰もいなくなった大きな滑り台をめがけて走って行った。
私は近くのベンチに腰を下ろして、尚人が遊ぶ姿を見ていた。
「あの、すみません、ちょっといいですか?」
見ると、ひとりの女性が立っていた。
「わたし、すぐそこに2ヵ月前に越して来たんです。」
私は黙って尚人を見ていた。
正直、砂場の件の後で、誰かと話す気になれなかったのだ。
「あ、突然ごめんなさい…、私、後藤さゆりと言います、あの、
少しだけお時間いただけませんか?」
ここまで言われて無視はできなかった。
「お一人ですか?」と聞くと、彼女は突然「シューン」と大声を張り上げた。
「ママー、僕は尚人君と遊ぶからね~!」
私達の目の前を、尚人と同じ位の男の子が大はしゃぎで走り去って行った。
「あれ、うちの息子、見ての通りやんちゃ坊主。」
そう言って、彼女は首をすくめ、おどけた表情を見せた。
「隣、どうぞ。」
彼女をベンチに座らせて話を聞くことにした。
後藤さゆりと名乗る彼女は、ベンチに座るなり由美子の事について
淡々と話し出した。
「息子とこの公園に来るようになって、まだ2ヶ月も経ってないんですけど…
初めの頃はまだ尚人君ママもいらしてて、私、何度かお会いしたんです。」
「…。」
「でも、彼女はいつも一人で…、周りから避けられている様子でした。」
私は、突然何の話を聞かされているのか分からずに困惑した。
後藤さゆりは、由美子が最近、公園に来ていないと言っている…。
それに、そもそも由美子が避けられているとは、一体どういう事なのか。
由美子は学生の頃から面倒見が良い姉御タイプで、
誰からも好かれる優しい子だった。
私のような陰気の変わり者が、人並みの学生生活を送れたのも由美子が
友達でいてくれたからだ。
「でも、彼女はいつも凛としていて…、隼人君を背中であやしながら、
尚人君をこの公園で遊ばせていたんです。」
そこで、彼女が声のトーンを落として言った。
「でも、胡桃ちゃん事件があってから来なくなってしまって…、
今日尚人君が来てたから会えるかなと思ったんだけど…。」
「胡桃ちゃん事件?」
「えぇ、あ、あの…、何もご存じないの?」
流石にここまで話を聞いて、名乗らないのもおかしいと思い、
由美子の友達だと話した。
ふと公園内に目を向けると、彼女の息子と追いかけっこをしながら、
声を上げて笑っている尚人がいた。