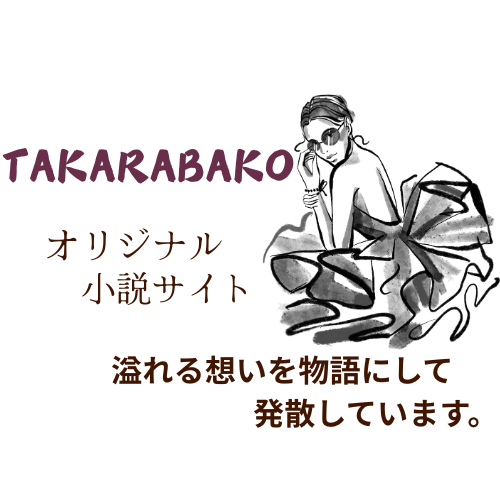「美~香さんっ!」
びっくりして見上げると、目の前には吉川夏美が呆れ顔で立っていた。
「どうしたの?箸を持ったままボ~ッとしちゃって。」
そう言って、不意に私の耳元に顔を近づけ、囁いた。
「昨夜はそんなに良かった…?」
「え…?何言ってるのよ、もぉ!」
「わーい、美香さんが怒った。」
吉川夏美は楽しげにそう言って、私の正面の席に座った。
「なんで喜んでるのよ、変な人ね。」
「あ、まだ怒ってる、ぼ~っとしてたり怒ったり、美香さんって
ホント面白いなぁ~。」
「そうやって、馬鹿にしていればいいわ。」
私はそっぽを向いた。
向かいの席で彼女は、クスクス笑いながら定食を食べ始めた。
「ところで、さっきから美香さんって呼んでるけど。」
「そうなの、気付いた? だって私、時々旧姓で呼んじゃうから…。」
「別にどっちでもいいわよ。」
「いや、それも失礼かなっと思ってね、名前で呼ぶことにしたから、
美香さんも私の事名前で呼んでよね。 決まり!」
「いいけど、美香さん、って、なんだか変な感じだわ。」
「あ、やっぱり? 実は私も変な感じしてたんだよね。」
「ふふっ、何よそれ、じゃあ、美香でいいわよ。」
「オッケー! じゃあ、私の事は夏美ね。」
「はいはい。」
小さなガッツポーズでにこっと笑った彼女に一瞬ドキッとした。
あぁ、思い出した…、私が夏美を苦手だった理由。
夏美には昔から、周りの人を惹きつける魅力があった。
大勢のアイドルグループの中でも、ひと際目立つ人がいる様に、
夏美はどんな場所にいても圧倒的なオーラを放っている。
大袈裟に言うとそんな感じだ。
昔から人前に出ることが苦手で、ひっそりと自分だけの世界を楽しみ
生きてきた私にとって、まさに太陽のような存在でいささか鬱陶しい。
なのに、何故だろう…。
私は今、そんな夏美の明るさが妙に心地よくて救われるのだ。