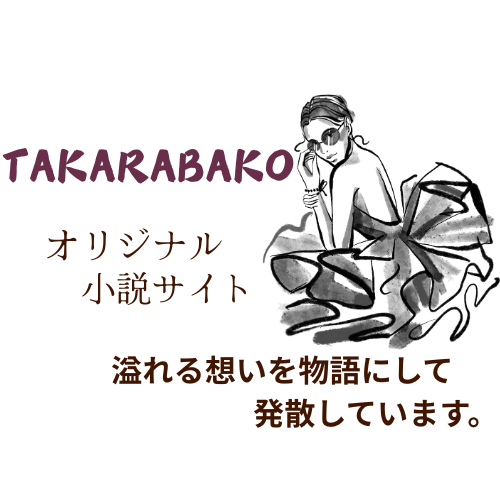父は数分前の出来事を覚えていない。
前に母が言っていたことを思い出す。
「まるで本のページをめくるように忘れちゃうのよ」
母らしい綺麗な表現でその時は笑ったけど、一緒に暮らしたら笑い事では
なくなった。
母は、認知症を知るために、何冊か買った本のうち一冊を私に渡した。
「美香も見ておいて」
ピンクや緑の蛍光マーカーが所々にひいてある。
「怒ったり問いただしたりすると認知症が悪化するからよくないって
書いてあるの」
と母は私に言った。
「へ~、そうなの。」
私はそっけなく返した。
認知症患者に、「もう忘れちゃったの?」「何でこんなことしたの?」と
感情的に怒ることが良い方法だと思っている人間が、果たしてどれ程いる
だろうか。
出来れば天使のように「いいよいいよ。大丈夫だよ」と、いつでも言える
人間でありたいと思うのではないだろうか。
しかし、それはとても難しい。
家族ならなおさらだ。
だから、敢えてそれが本に書いてあるのだろう。
父は新聞を持ったまま居間を出て、縁側にあるロッキングチェアに腰を下ろした。
縁側からガラス越しに見えるのは、父のお気に入りの庭だ。
「お父さん、そこは身体が冷えるわよ。」
私がそう声をかけると、父は誰もいない台所に向かって言った。
「お母さん、僕の毛布を持ってきてもらえますか?」
返事がない事に気付いた父が、私に「お母さん、いないのか?」と聞く。
私はこんな時、父に何て言ってあげたら良いのか分からなくなる。
「今、ちょっと出かけてるの。」
そう言いながら、急いで父の書斎に行き、厚手のひざ掛けを持って来て、
それを父の膝に掛けた。
「ありがとう。」
父はそう言って背もたれに寄り掛かり、ゆっくりと椅子を揺らした。