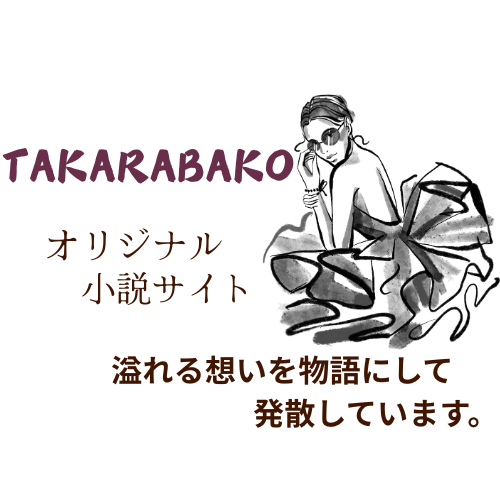あの衝撃的な出来事があった夜、「おやすみ」のLINEにリナからの返信は
なかった。
翌朝も、その日の夜になっても俺からのLINEは既読スルーのままだった。
こんな事は初めてだ。
そもそも、リナとは喧嘩をした事がなかったから、既読スルーをされるなど
経験したことがなかった。
しかも、厄介なことに、今回の出来事を俺が知っているという事を、
リナは知らないのだ。
俺が直接、彼女に何かをしてしまったのなら、それに対して誠心誠意
向き合うなどの対策が出来るけど、今回はどうしたらよいのか分からない。
酔ったタカヤに言い寄られて、ショックを受けた気持ちは
分からないでもない。
ただ、なぜ俺からのLINEに、返信が出来ないのかが、分からなかった。
事情を知っているだけに、とぼけて彼女に会いに行くことさえ、何となく
躊躇してしまう…。
あぁ、なぜあの日、あんな場面に遭遇してしまったのだろう…。
…いや、むしろ遭遇して良かったのだ。
自分の知らないところで、あんな事が起きていたなんて想像しただけで、
ゾッとする。
そして気付けばあの日から、3日も経っていた。
俺はああでもない、こうでもないと頭を悩ませながら、会社に着いた。
朝礼が終わると、社長が俺の席まで来て「調子はどうですか?」と尋ねた。
「はい、順調です。今月も頑張ります。」
俺が答えると、社長は満足げに頷いた。
「柏木リーダー、そろそろ松島君も法人契約が獲れないといけませんね。」
「法人?」
「企業保険よ、そっちの方が報酬もでかいの。」
隣の結子さんが小声で呟いた。
「承知しました。」
リーダーが答えると、社長は暫く社員の成績グラフを見上げ、
静かに社長室に入っていった。
「それじゃあ、10分後に研修室に来い、とりあえず今日は20分間な。
商品の基本的な知識を教えるから1回で覚えろよ。」
「はい、よろしくお願いします。」
「ふふ、スパルタ研修が始まるわね、頑張れよ。」
「はい、ってか、もう慣れましたけどね…。」
結子さんとの会話の後、俺は急いで1階の外に設置してある
喫煙コーナーに入った。
今朝、リナに『おはよう、今日いつものカフェで会えない?』と
LINEをしておいたが、未だ既読になっていなくて、流石に落ち込んだ。
リナの前では控えていた煙草をくわえ、ニコチンを思い切り肺に
流し込んで、煙をゆっくりと吐いた。
「いったいどうしちゃったんだよ、リナ…。」
リーダーのスパルタ研修を終えると、俺は結子さんにLINEを入れた。
そして、一旦脳内を仕事モードに切り替え、会社を出た。
午前中の商談を終え、会社の近くにあるイタリアンカフェに入った。
奥の席で結子さんが手を振っている。
「すみません、遅くなっちゃって。」
「いいよ、言ってたメニュー、頼んどいたよ。」
「ありがとうございます。」
「それで、彼女から連絡来たの?」
「いや、まだです、今朝送ったのは未読のままだし。」
「あら、だってあれからもう3日でしょ?深刻ね…。」
俺は今回の事でどうしたらいいのか見当もつかず、先輩の結子さんに
相談することにしたのだ。
俺がこの仕事をやる気になった理由を知っているのは、社長と、
あの時電話の声をすぐ横で聞いていたリーダーと結子さんだ。
結子さんは、俺の恋愛話に興味津々で、色々聞き出すのが上手い。
俺も浮かれていたせいか、ポロッとリナとの馴れ初めを話してしまった。
そんな事から、俺と結子さんはお互いのプライベートの話を時々
話す程の仲になった。
料理が早速運ばれた。
俺はリナの美味しそうに食べる姿を思い出し、急に寂しさが込み上げた。
「なんて顔してんのさ、松島君は何も悪い事してないじゃん。」
「そ、そうなんですけど、だから余計に分からなくて…。」
「まぁ、とにかく食べて元気出そう、ほら、旨そうだよ!」
俺は気を紛らわそうと料理をガツガツ頬張った。
「うまいっすね、これ。結子さん、ゴチになります。」
「ふふ、いいよ、松島君に早く元気になってもらわないと、チームの
成績にも影響するからね…、そこは協力するわよ。」
「やった。」
「ねえ、彼女の写真、見せてよ。」
「え、まぁ、いいですけど…驚かないで下さいね。」
「はいはい。」
俺はリナの笑顔の画像を結子さんに見せた。
「へ〜、可愛いじゃない。」
「でしょ?」
俺は得意げな顔で結子さんからスマホを受け取った。
「ねえ、付き合って何年だっけ?」
「えっと、2年目ってとこですかね。」
「私が男だったら…男だったらよ?彼女の事、束縛しちゃうかも…。」
「ハハ、結子さん、もう男の目になってますよ。」
「松島君、私の予想だけどね…、たぶん彼女も自分の可愛さを分かってると
思うのよ…、でもね、実際のところは、自分の笑顔がどれだけ男を夢中にさせているか、分かっていないと思うよ。」
「は、はい。俺もそう思います…、けど、それが?」
「だってさ、こんなイケメンの松島君でさえ、彼女にアタックする時すっごく
緊張したでしょ? 実際、あんな腑抜けになってたくらいだもの。」
「まぁ、そうですね…、やばかったです。かなり勇気要りましたよ。」
「…ってことは、同級生のタカヤ君も、ずっと勇気がなくて言えなかったのよ。
もしかすると、彼女の周りには他にも彼みたいな男がいるかもね。」
「ちょっと、結子さん、脅かさないでくださいよ。」
「彼女は、そこまで自分の魅力に気付いてないのね…、純粋な子なのよ。」
俺は呆気にとられて結子さんを見ていた。
「結子さん、洞察力、エグイです…、参ったな。ドキドキしてきた。」
「分かるわ、その気持ち。私の夫もモテるから大変なのよ。」
「あ、は、はい、そうでしたね…。」
急にいつもの結子さんに戻って、力が抜けた。
「でもね、彼は今のところ、私に夢中だからいいんだけどね、うふっ。」
「結子さん、なんか、ありがとうございました。それで、結局どうしたら
良いんですかね…、」
「決まってるでしょ、会いなさい。今は一人にしちゃだめよ。」
「は、はい!」
店を出ると、俺はリナにLINEを送った。
『今夜どうしても会いたい。リナのアパートの前で待ってるから。』
タカヤだか何だか知らねーけど、リナの事は諦めてもらうからな。
そして俺はその日、ある事を決心した…。