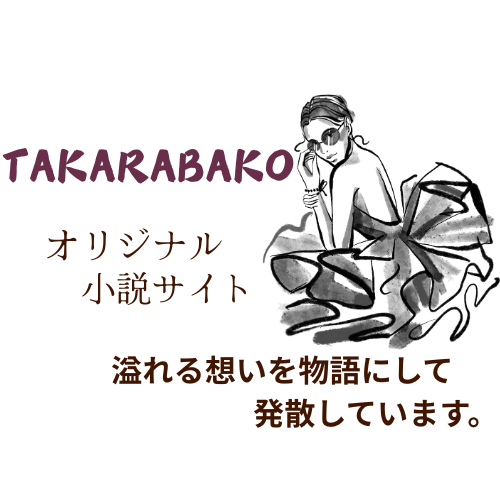「ケチャップ…ついてるよ、ここ。」
リナは、自分の口元を指でツンツンして見せた。
俺は彼女の顔を見ながら、自分の口元を指で探る。
「ほれっ!」
ケチャップが付いた指を、彼女の鼻先に突き出して見せた。
「もぉ! やると思ったわ、ホント子供ね…。」
そう言って彼女はニヤッと笑って、片方の頬だけエクボを見せた。
「リナはこの後、なんか予定あるの?」
彼女はパスタを巻いたフォークを口元でいったん止め、
「う~ん、何かあったかなぁ~?」
と小首をかしげた。
「何もないって顔だな…。」
「あるかもしれないわよ。」
リナがいつもの様に得意顔で言う。
「僕の部屋、来る…?」
「どうしようかな~…。」
「嫌なら別にいいけど。」
わざとそっけなく言うと、彼女は少しはにかんで
「行こうかな…。」と言う。
付き合って1年経った。
そして俺は、未だこんな風にしないとリナを部屋に誘えない。
何故ならリナは、俺が今まで付き合ってきた女の子達とは
比にならない程、『可愛い女』だからだ。
彼女は部屋に入るなり、転がっているペットボトルを拾い上げた。
「もう、この前掃除したばっかりなのに…。」
そのうち台所のワゴンからスーパーの袋を持って来て、
部屋のあちこちに落ちているゴミを入れ始めた。
俺は、いつもの様にベッドに寝ころんだまま、部屋中を手際よく片付け、
動き回っているリナを、ただじっと眺めていた。
「はぁ、キレイになった! でもこれ、あと何日もつかしら。」
「もって3日ってとこだけど…頑張るよ、サンキュー。」
「ほんと、感謝してよね。」
俺の前で仁王立ちしたリナが、ほっぺを膨らませて睨んだ。
そんなリナの手を握って、強引にベッドの中へ引きずり込む。
彼女はいつだって、初めは両手をバタバタさせて抵抗するけれど、
そのうち、まるで子猫の様に俺の身体に絡みついて甘えてくる。
リナは、その透き通るような白い肌と妖艶さで、俺を容赦なく魅了した。
「私のこと…好き?」
腕の中でリナが聞く。
「好きだよ。」
そう答えると、リナは「嬉しい…。」と耳元で囁いた。
俺は思わず彼女の身体を強く抱きしめる。
この女を絶対離したくない…。
狂おしいほど彼女に溺れていくこの感情を
抑えられなくなりそうで怖くなった。