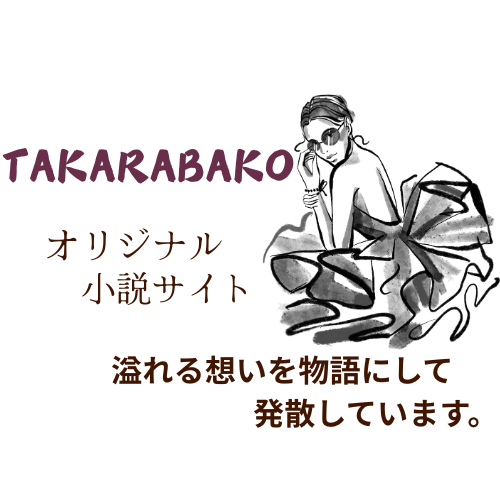その店は、地元で人気のカフェバーだった。
店内は広く、中央にカウンター席が並んでいる。
店の奥まで進むと、由美子がテーブル席から手を振った。
私は遅れてすみませんと言って、空いている由美子の隣に座った。
正面に座っていた武史が、私に向かって簡単な自己紹介をした。
そして彼は、少し顔を赤くして私に言った。
「実は美香さんにお会いしたくて、彼らにお願いしたんです。」
「え…?」
「だから言ったでしょ、彼があんたを気に入ったって。」
横に座った由美子がすかさず耳元で囁く。
私はてっきり由美子達の思惑だと思っていたのだ。
それにしても…。
目の前で、はにかんだ笑顔を見せる武史は、驚くほど
私の理想と合致していた。
かるくパーマのかかった髪、切れ長で澄んだ瞳、笑った時に
見える綺麗に並んだ白い歯、すべて完璧だった。
「ちょっと、美香ったら見すぎよ、日高さん困ってるわ。」
「あれ、もしかして僕たちお邪魔かも知れないですね」
「おいおい困るよ、君達は僕の応援団なんだからね。」
ふざけて席を立とうとする後輩夫婦を、彼が引き止めた。
恥ずかしさで困惑していると、彼が不意に言った。
「美香さん、僕の事覚えていませんか?」
私が由美子の顔を見ると、両手を顔の前に小さく合わせて
「ごめ〜ん」と囁いた。
まったく覚えていないが、武史とは由美子の結婚式で会っていたのだ。
当時の私は、最初の旦那との結婚が決まった頃で、幸せの絶頂にいた。
ウェディングドレスを身にまとった由美子の姿と、数ヶ月後の自分の姿が重なり、
祝福の気持ちと幸せな気持ちでいっぱいだった事を思い出す。
翌日、今回の経緯を全部話すからと、由美子が家にやってきた。
「実はね、日高さん、結婚式の二次会で美香に一目惚れしたんだって!」
由美子は興奮した様子で話し続ける。
「でもね、美香が左手に婚約指輪してたでしょ?
だから、声をかけるのを諦めたんだって。」
「で、先週、台湾のお土産持ってきてくれた時に、
また美香の事を聞かれたってわけ。」
「そうだったのね…、そんなこと、全然気付かなかったわ。」
「ねえ、日高さんってまさに美香の理想のタイプじゃない?
私知ってるんだからね、フフフ。」
「私、そんな…別にタイプじゃないわよ。」
由美子に言い当てられて、恥ずかしさのあまり慌てて否定した。
久しぶりの恋バナで、女子高生のようにはしゃいだ由美子は、
上機嫌で帰って行った。
ベッドに仰向けに寝転んで伸びをした。
携帯の連絡先リストに追加された彼の番号を眺める。
時折見せた武史のはにかんだ笑顔を思い出しながら…。